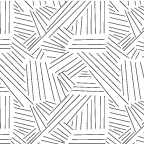前回の記事(「長期的ルーブリックとしての卒論ルーブリック」)のポイントは
長期的ルーブリックでは、能力を細分化して記述するのではなく、
学生の実際の学びの文脈を念頭に置きながら、
観点を設定するのがよいだろうということであった。
我々の通常の行為(パフォーマンス)は複数の能力から生み出されている。
それならば、わざわざその能力を細分化するのではなく、
実際の文脈で生み出されるパフォーマンスを評価し、
そのパフォーマンスがどのような能力から生み出されるのかを考えることで、
能力を間接的に評価できるのではないか、ということであった。
また、実際に提案した卒論ルーブリックでは、
学生のつまずきを念頭に置いているという点も重要であった。
学生がどのような点でつまずいており、
そのつまずきはどのような努力によって克服できるのか、
この点を示すことにこそルーブリックの意味があるのだろう。
さらに、そうしたルーブリックが教員による評価の場面でも
実質性を帯びてくることは言うまでもない。
こうしたことが正しいとするなら、
以前に書いた記事(「ルーブリックの仮説性について」)における
次の疑問にも答えられるだろう。
「ルーブリック自体のテストに用いることができるエビデンスは、ルーブリックで評価する場合には必ず生じているものなのだろうか」
たとえば、ルーブリックを用いて評価をした場合、
どのようなときにそのルーブリックはよいルーブリックで、
どのようなときにそのルーブリックはよくないルーブリックであると言えるのか。
「評価がしやすいかどうか」というのはもちろん重要なポイントであるが、
それでもなお、ポイントを欠いているように思える。
しかし、先の議論からすると、
ルーブリックのよしあしのテストの基準は端的に次のように言えるのではないだろうか。
「あるルーブリックがよいルーブリックであるのは、そのルーブリックが学生の典型的なつまずきを記述しており、かつ、そのつまずきを克服するための明確な次の一手が示されている場合である」
もちろんこの基準に沿っていれば、「評価しやすかった」ということにはなるだろう。
しかし、教員にとって評価しやすい基準が
学生の形成的な学びにとっても意味をなすかどうかは別問題である。
学生とともにルーブックをつくることが望ましいのは、
まさにそのギャップを埋めるためである。
しかし、学生とともにつくったとしても、
先の「つまずき」という観点が共有されていなければ
やはりそのルーブリックは有効なものとはならないだろう。
そうすると、この前の記事で回答を曖昧にしていた次の問題にもはっきりと答えることができる。
「ルーブリック自体のテストに用いることができるエビデンスは、ルーブリックで評価する場合には必ず生じているものなのだろうか。
生じているものの、利用している教員がテストしていないだけなのか、あるいは、ルーブリックの構造(観点の設定の仕方や記述の仕方)によって、生じる場合があったり、生じない場合があったりするのだろうか。」
この前は、後者であると考えていたが、今では前者であると考えている。
先の「つまずき」という観点を導入することで我々は常にルーブリック(それがどんな構造のものであれ)のよしあしについてテストできるのだ(それは今から考えれば当然のことであるが)。
自分がこの前、後者であると思っていたのは、まさによしあしのチェックポイントである、「つまずき」の観点が含まれているかどうかというよしあしの基準と混同していたためであると思われる。